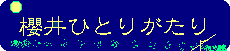「契り」
「最高の眺めって聞いたから、ついてきたのに」と、娘はグチをこぼした。
それはそうだろう。目に映るものといえばカシやタブなどの照葉樹、秋らしい色づきは下生えのひょろりとした木々の葉にやっと見られるだけだ。せっかくの秋晴れも、木の間に片れ端を窺う程度。
「まあ、そう言わずに。がまんした分だけ、大きな感動が待っているんだ」
「また出た、父さんの『がまん』ってセリフ。自分はおいしいビールが待ってるからいいけど、お茶しか飲まない私たちは、たまったものじゃないわ。ねっ、そう思わない」
娘は、すぐ前を行く母に賛意をもとめた。
「いいえ、きょうの私は父さんの味方。あなたも子供じゃなんだから、いい加減がまんの良さも知らなくちゃ」
そう言う母親も、内心では娘を気の毒がっていた。秋とはいえ快晴の正午前、亜熱帯樹層の林の中は温室のごとく蒸し暑い。どこかでソヨゴを騒がす風も、彼らのふところには届かない。登山道には足掛りの丸太が埋め込まれている。けれどその間隔は、小柄な娘の歩幅には広すぎた。かえって脚の疲れをまねいているに違いない。
案の定、娘はそれっきり押し黙った。父母は、わが子の不満を背負って歩き続ける。汗が胸を伝う。こむらがだんだん固くなる。
それでも彼らは立ち停まらない。「休もう」と言いだすきっかけを、たがいに見失ったようだ。娘も、いまはひたすら山頂を待ちこがれている。
前に仰ぐ緑葉の繁りがうすくなった。「あと少しだ」と父親が言った。娘が「ふう」と息をついた。機嫌の悪さは、すでに忘れたらしい。
石段が見えてきた。粗い石組みの隙間をシダが覆う。くぼみに溜った黒土に、ノギクが花を咲かせている。足早に二十段あまりを登りきると、朱のはげた鳥居の下で父親は振り返った。「ほら、見てごらん」という声に、母子は足を停めてしたがった。
「まあ」母親が、声で驚きを表した。娘は無言のまま、額にはりついた前髪を指で払った。
空は、墜ちそうなほど濃い青を湛えていた。はるかに一線、刷毛で描いたような雲が浮かぶだけだ。その青を支えるように、なだらかな尾裾をひく山がふたつ、乳房の形容ふさわしく視野の左右に位置している。ふもとでは、刈り入れを待つ晩稲の穂が、ゆるく金色を波打たせていた。
「モミジのさかりには早かったね。でも充分にきれいだろう」
母親がうなずく。娘はまだ、ほぐれない前髪を気にしている。
そこは、神社と呼べるような場所ではなかった。秋草生い茂る塚を背に、身の丈ほどの祠。その斜め手前に自然石の碑が二基並んでいる。みなで祠を拝んだ後、娘は不思議そうな顔で碑のまわりを廻り、父親に問いを発した。
「ねえ、ここってお墓?」
「そう、千年以上前に死んだ人のお墓だ」
「なんだか気味が悪い」
「だいじょうぶ、化けて出ないよ」
「そうじゃなくて、左側の碑は、ふもと向きに名前が刻んであるのに、右側のは山向きに刻んである。なんだか、辺りの土地ぜんたいに背を向けてるみたい」
「それはね――」と父親が言いかけた時、見晴らしよい場所を選んだ母がふたりに声をかけた。「さあ、お弁当にしましょう」
レジャーシートの上、お茶を飲み、おにぎりをほおばる。
「あれ、ビ-ルは」娘が父に訊く。
「ここは清浄な場所だからね。日本酒ならいいかもしれないが」
「それはそうと、さっきの話だけど」
「さっきの話、って?」母親が言葉をはさむ。
「墓碑の銘のことさ」と、父親が答える。
「ああ、銘の向きね」
「なんだ、母さん知ってんの。だったら教えてよ。私だけ知らないなんて、バカにされてるみたい」
「右側の碑はね、さる皇子様のものなの。本当は帝になられる方だったんだけれど、それを妬んだ人に無実の罪をきせられ、殺されてしまったの」
「どうして後ろを向いてるの」
「国の人々が、崇りを恐れたんでしょう。自分たちに禍いを投げかけませんように、って」
「左側は?」
「皇子の奥さん、つまり、きさきとなるべきだった方よ」
「その人はどうなったの」
「皇子のご葬礼の日に亡くなったわ。悲しみのあまり、ご主人の跡を追ったの」
「かわいそうなお話ね。でも、ふたり死んでからも互い違いに向けられるなん
て、もっとかわいそう」
「奥さんはずっと、背を向けた皇子に里の様子を語りかけているのよ。『あな
た、そろそろ向かいの山が色づくころですよ。田のあぜ道では、ススキの穂を抱えた子供が遊んでいます』ってね」
「ふうん」娘は、あいかわらず無感動な顔を、ふもと側に向けた。
会話に間があいた。父親の、喉を鳴らして茶を飲む音だけが耳につく。
やがて娘が口を開いた。「トンボ、たくさんいるのね」
両親の目が、娘と同じくふもと側に向けられる。
「ああ、アキアカネだろう。でもおかしいな。この時季には、もう里へ下りているはずだが」父親がつぶやく。
娘のまなざしが、さらに正面を飛ぶ群れに注がれる。遠くは黒く、近くは赤い無数の点が、せわしなく宙を舞っている。じっと見ていると、右から左に目で追ったはずが、いつのまにか逆に進んでいたり、奥のものが手前の群れを抜け、いきなり近くに迫ってきたりする。
軽いめまいを憶え、娘は視線を手元に戻した。すると、半分食べかけのおにぎりに、アキアカネがとまっていた。別に追い払う気もわかず、娘はそれを凝視した。
トンボは二三度、機械じみた動きで首をひねった。――コメのごはんも食べるのかな、と他愛ないことを思った瞬間、手品のように宙に浮かんでいた。
その後もしばらく、娘はおにぎりを見つめていた。白いご飯粒に、なおも鮮やかな茜色が留って視え、それが不思議でならなかったのだ。
「どうしたの。もう、おなかがいっぱいなの」という母の声で、娘は我に返っ
た。
「ううん、なんでもない」と答え、彼女はおにぎりを口に運んだ。
* * *
親子は山を下りる。父親は、はるか先頭を上機嫌で歩く。後ろでは、肩を並べて歩く娘に、母親が言葉をかけていた。
「ねえ、あなたトンボのとまったおにぎり食べたでしょ」
「なんだ、母さん見てたの」
「ええ、知ってて声をかけたわ。そしたら、あなた食べちゃった。気持ち悪くなかった」
「それはなかったわ。ただ……」
「ただ、なあに」
「トンボの赤がご飯に映って、まるで人の血みたいだった」
「人の血だったら、なおさら気持ち悪いじゃない」
「それが、そうじゃなくて―――これはあの人の、きょうお詣りした皇子の血じゃないか。あの人も奥さんも、きっと私に血を託したがっている。自分はすすんで、それを受け入れなきゃ、って思ったの。私、頭がおかしくなったのかしら」
「いいえ、ちっともおかしくないわ」母は娘の肩に手を回し、続く言葉を耳元にささやいた。「それはあなたが女だから。とっても優しい女だから」
娘はいっしゅん驚いた表情をみせた。が、すぐに普段の平静を取り戻して母に訊ねた。
「母さんも、父さんの血を受け止めたと思った?」
「ええ、もちろんよ。その時、とっても幸せだったわ」
娘は軽く頬を赤らめた。
少しこそばゆい秘密を分かちあい、母子はまた歩き出した。父親はさらに先を歩いており、幹や梢に姿も遮られがちだ。その陽気な鼻唄を、ふたりはときおり目くばせしては笑い合った。
了
|